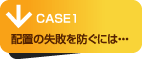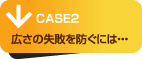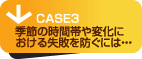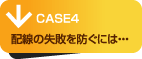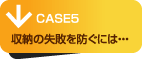配置そのものの失敗は、普段の自分の生活を間取りに反映させていないから。
間取りを作ったら、自分や家族の生活ぶりをリアルに想像してみましょう。
間取りにも流行がありますが、それも容易に取り入れるのではなく、自分たちの生活に本当に必要かどうか見極めることが大切です。
ライフスタイルの変化によって、室内も変化できれば快適さはずっとアップします。
そのためには、あまり用途を決めすぎた部屋をつくらないことが重要です。
玄関や階段、浴室など将来もあまり位置を変える必要のない部分をつくり込み、
その他の部分は、あまり細かい部屋割りにせず、そのときどきの家族構成や生活に合わせて仕切ったり、模様替えすると使いやすく楽しみも広がります。
意外なようですが、プランニングは外から中へ決めていくのが間違いがありません。
まず土地の方角。日当たりの良し悪しで、リビングや水まわりの位置が大方決まってきます。
また、隣家との距離が近い場合は、窓やドアなどの開口部の位置にも注意が必要。
隣家の換気扇の前に窓をつくってしまうと、ニオイや煙が家の中に入ってきてしまいます。
逆もまたしかり。気持ちのよいご近所付き合いのためにも考慮したいポイントです。
さらに、道路に面した部屋の場合、プライバシーを考えて窓の位置や大きさを決めることも気持ちよく生活できるためには必要なことです。
メーカーからもらう図面はたいてい北が上。
しかし、
これを逆さまにして南を上にしてみると、また違った角度から間取りを点検できます。
北が上の場合は「家の外から中を」見ている感覚に近いですが、南が上の場合は「家の中から外を」見ている感覚に近いことがわかりますか?
実際に生活する場合は、こちらの感覚に近いのです。
決まった方から図面を見るだけでなく、ひっくり返したり横にしてみたり、角度を変えながらチェックすると、気付かなかったことが見えてくるかもしれません。
実際の広さの50分の1か100分の1で描かれた図面からは、実際の広さがイメージしにくいもの。しかも、人間の頭は良い方に想像しがちで、たいてい実際より広くイメージするのだそうです。
そこで、紐などを実寸サイズに切り、それを今の部屋と比べてみましょう。
よりリアルに広さが実感できるはずです。
また、生活する際には家具を置くわけですから、部屋そのものの広さだけではなく、
家具を置いて考えることが大切です。
家具を置くと思ったより狭くなってしまった…という失敗を防ぐためにも、
図面に合わせて縮小した家具の切り抜きを作り、図面の中に配置してみましょう。
意外と幅を取っていたり、開口部との兼ね合いで設置できない場所がおのずと見えてくるはずです。
開口部と家具との関係はかなり重要なポイントなので、
家具に合わせて開口部の位置も再度確認しておきましょう。
また、シンプルな動線を心がけることも需要です。
動線とは、家の中での人の動きの流れのこと。これは各自のライフスタイルによっても大きく異なります。
家族がそれぞれ一日の自分の動きを思い出しながら、間取りに線を書き込んでいくとわかりやすいでしょう。
とくに線が重なる部分は距離を短くするなどの工夫が必要。
不必要な回り道や遠回りになっている線にも注意。個室以外は、
できれば2つ以上の出入り口があると流れるように人が動けて快適です。
周辺環境は時間や曜日によって変わるもの。
陽当たりに関しては、事前に住宅会社に頼んで日照時間や日照角度を計算してもらうようにしましょう。
季節や時間帯によって陽射しは変わりますから、それをふまえずに間取りを
決めてしまうと普段の生活に不便が生じてしまいます。
建築家や設計士は、やはり何軒もの家を建ててきたプロです。
そのプロのいうことに素直に耳を傾けるのも重要。自分では「完璧な間取り!」と思っても、
それがイコール住みやすさに繋がるかといったら、そうでもないことも多いそう。
自分のライフスタイルやこだわりたい部分をしっかり伝えて、あとはプロにお任せすることも必要です。
また、騒音も見逃せないポイント。交通量の多い道路に面した土地や、繁華街に近いところは‘いつ、
どのくらいうるさいのか’を事前に調べておくと安心です。
そのためにも、下見はなるべく様々な時間帯に足を運びましょう。また、近所の人に尋ねるのも有効です。
プランニング失敗談でも上位を占めるのが、この配線に関するもの。
家全体の間取りという大きなスケールでものを考える場合、
配線はあまりに細かいところであるため見落とされがち。
しかし、実際に生活する上で電気を使う場面は非常に多いため、ここを失敗してしまうと
日常生活への影響は大きいのです。
また、近年ではインターネットやテレビに関する‘情報配線’の失敗が増えています。
2010年のテレビ放送デジタル化に向けて多チャンネル化が進んでいるため、
それに対応するためにテレビを置く部屋には先行配線を行っておきましょう。
後でケーブルを引き込むと工事費もかかり、せっかくのインテリアも台無しです。
家が建ち生活を始めてから「ここにもコンセントが必要だった!」などと後悔することがないよう、
細かい部分ですが、しっかり考えて使い勝手のいい我が家をつくりましょう。
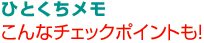
一般的な目安としては、2畳につき2口。しかし、パソコンを使ったりAV機器を楽しむ部屋ではこの量だと少ないので、余裕を持たせましょう。
収納に関しては大きければいいというものでもなく、一般的には床面積の
10%~20%が必要とされています。収納するものにふさわしい大きさと位置が重要となります。
普段使うものは使う場所に収納し、季節のものやたまに使うものや各部屋からはみ出たものをある程度
集中してしまうためのスペースを設けるのが基本です。
出しやすくしまいやすい収納が、すっきりした住まいへの第一歩。
図面上では収納をとるとその分部屋が狭くなりますが、あとから家具を買い足すよりも
見た目・性能共に心配がありません。
手持ちの家具も上手に利用しましょう。
また、子供が小さいうちはモノも少ないですが、成長するにつれ多くなってきます。
今の持ち物だけでなく、将来を見越した収納スペースが必要です。
「どのように収納を計画するか」も、プランニングの重要なポイントです。
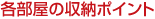
| 玄 関 | 靴の他に、出掛けに羽織れる上着やゴルフバッグなど、玄関近くに収納したいものは結構あります。最近人気があるのは、三和土からつながるシューズクローク。車庫にもつなげると雨の日も濡れずに出入りができて便利。 |
|---|---|
| 廊 下 | 階段下のスペースは奥行きも深く取れるので、掃除機や古新聞・古雑誌といった雑多なものをしまうのに重宝します。充電式掃除機の場合は、充電用のコンセントを付けることも忘れずに! |
| リビング | ビデオやDVD、CD、雑誌、リモコンといった細かいものが散乱しがち。家族の誰もが使いやすく、また来客時にさっとしまえるような収納が理想的となります。見せる収納と隠す収納を効果的に使い分けよう。 |
| キッチン | 鍋などの調理器具、食器の他に、食料品のストックなど収納物が多いキッチン。使用頻度の高いものは手の届きやすいところに、あまり使わないものや重い家電などは下に収納すると良いでしょう。 |
| 洗面所 | タオルや洗面道具の他に、下着も収納できるスペースを作ると着替えの際に便利。 |
| トイレ | 予備のトイレットペーパーや掃除道具がしまえる収納があると、見た目もすっきりします。 |
| 寝 室 | 最近では収納力抜群のウォークインクローゼットを設ける人が多い。また、ふたつの寝室の間に通路としてウォークインクローゼットを設ける方法もあり、通気性に優れ掃除もしやすいといったメリットがあります。 |
| 外部収納や 屋根裏など |
季節外の家電やたまにしか使わないアウトドア用品など、出し入れする機会の少ないものをまとめて収納しましょう。 |